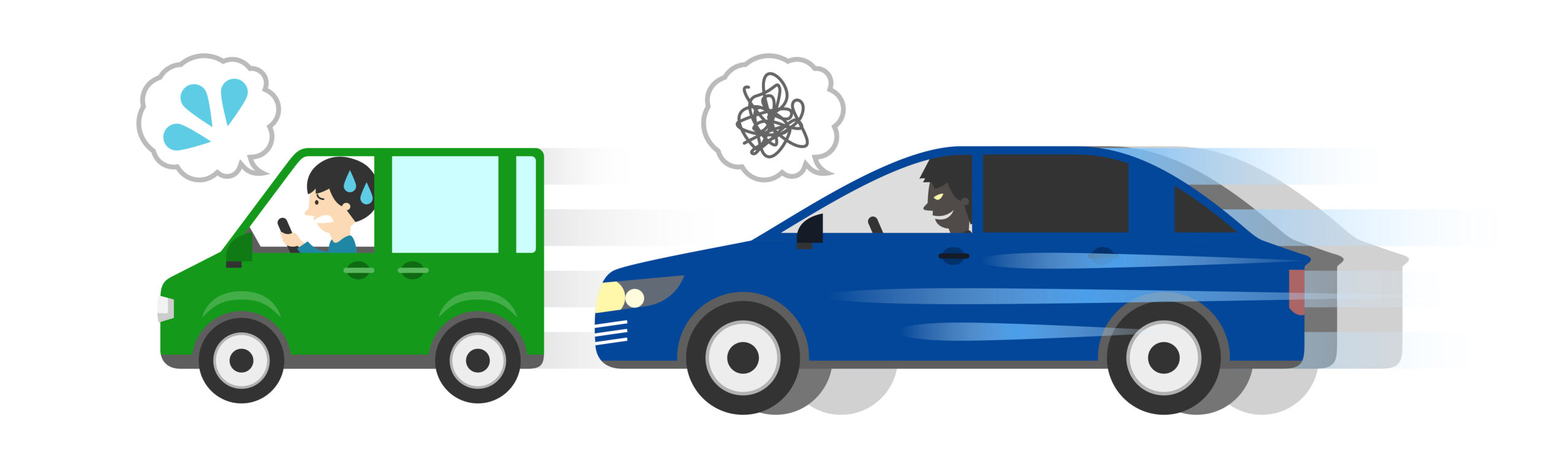あおり運転は危険で事故や交通トラブルの原因になりかねない妨害運転だが、あおり運転されたドライバーにもまったく非がないとは言い切れないケースも多い。つまりあおり運転の原因を作ってしまうドライバーもいるから、あおり運転によるトラブルや交通事故も増えてしまうという現実がある。
ここであおり運転を誘発するドライバーの自己中運転について代表例を挙げて解説する。自分がこうした運転をしていないか、またあおり運転を受けたと言うドライバーは、こうした運転できっかけを作っていないか振り返るとともに、交通トラブルを避けるためにルールやマナーを守った運転を心がけたい。
6. スマホを見ながら、電話しながらの「ながら運転マン」
運転中にスマートフォンでの通話・操作・視聴などを行う行為。前方不注意になり、車線逸脱や速度変化に気づかず周囲に不安と苛立ちを与える。
2019年の道路交通法改正により、携帯電話使用による交通の危険が生じた場合、「6点減点+即免停」の重罰化。極めて違法性が高い。
ハンズフリー通話での短時間の会話は許容される場合があるが、それでも注意力低下を伴う。画面操作・視聴・手持ち通話はすべてNG。
スマホは運転前にマナーモードまたは機内モードへ。ナビ使用時も音声案内のみで運転に集中することが必須。
7. ウインカーも点けずにいきなり強引に割り込み
合流や車線変更時、方向指示器(ウインカー)を出さずに、無理に間に割り込む乱暴な運転をするドライバーもいる。こうした運転は危険であるだけでなく後続車に驚きと怒りを与え、接触事故や煽り運転の誘発につながる。
道路交通法第53条により、進路変更時の合図(ウインカー)不使用は違法。重大な危険を伴う妨害運転にも該当する可能性あり。
緊急回避などやむを得ない場面以外で正当化は困難。日常的に繰り返すドライバーは、交通秩序を乱す加害者と見なされる。自分は普通に合流しているつもりでも、相手からは強引な合流と感じ取られる場合もある。
車線変更前には3秒以上前にウインカーを点ける習慣をつける。ミラーと目視で安全確認し、十分な車間距離があるときに行動する。
8. ブレーキを頻繁に踏む「チョンブレ」運転
渋滞でもないのに、必要以上に小刻みにブレーキを踏む運転。後続車にとっては「減速の意図が読めない」「無意味な停止が続く」などストレスになる行為だ。
これは車間距離を詰めてくる後続車に対して威嚇目的で行うケースもあり、トラブルの火種になることもある。自動運転・追従走行の車は急に反応し、逆に玉突き事故を起こすことも。また車酔いしやすい同乗者にも不快な運転だ。
アクセルとブレーキをスムーズに操作し、エンジンブレーキなどで減速。無意味なブレーキを避けるため、周囲の交通に目を配る。
9. 信号の青でもなかなか発進しない
信号が青に変わっても、前方車がスマホを見ていたり、ボーッとして発進が遅れる行為。後続車にとっては非常に苛立たしい。
ながら運転にはあたらないが、交通の流れを妨げ、無駄な信号待ちが発生する行為で、イライラした後続車による強引な通過や無理な追い越しにつながりやすい。無反応時間が長いと、クラクションでの警告や煽り行動の引き金になる。
信号待ちでの着信やメールのチェックは瞬時に済ませ、ダラダラ見ないようにしよう。青信号の切り替わりに意識を集中させ、すみやかに発進できる準備をする。信号待ち時にスマホを見る行為は、ついつい見続けてしまうような使い方は避けよう。

10. コンビニや駐車場から急に道路へ割り込む
道路に合流する際、ウインカーを点けずに、あるいは十分な車間がないのに強引に割り込む行為。後続車が急ブレーキを強いられることもある。
割り込まれた車が「急に割って入られた」と感じて反発しやすく、接触事故や車間トラブルにつながる。譲ってくれた車両に対する無反応(お礼なし)も苛立ちの原因になる。
合流前にウインカーを早めに出す。安全確認を徹底し、車間が十分空いたタイミングで入る。また譲ってくれた車両にはハザード点灯などで感謝の意を示す方がいい。
サンキューハザードが違反という意見もあるが、ハザードの目的外の使用で違反切符を切られたことなど聞いたことがない。パトカーも使っており、意思疎通のためには活用すべき行為だと思う。
ここで挙げた運転は「自分は悪気がなかった」としても、受け手次第では「挑発行為」「配慮不足」と受け取られやすく、煽り運転などの引き金になる可能性があります。運転では、「周囲からどう見えているか」を意識することが、不要な交通トラブルを防ぐ鍵になります。